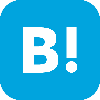もっと知りたい「ブリ」の入門知識
ブリは北海道の南から九州まで、日本各地の近海で見かける馴染み深い魚です。
ブリのプロフィールを見てみよう
出世魚であるブリは成長に合わせて名称が変わり、8kgを越える成魚となったものがブリと呼ばれています。
ブリは日本近海に生息しているため、比較的漁獲しやすい魚種であり、さらにとても美味しい食糧として昔から日本人の食卓に取り入れられてきました。
ブリの基本情報
ブリは、スズキ目スズキ亜目アジ科ブリ属に分類される海水魚です。
ブリの体型はラグビーボールのような形をしており、丸みを帯びた厚みがあります。
ブリの寿命は7~8年 と言われており、孵化してから5年ほどで体長1mくらいまで成長し、体重は15㎏前後まで成長する大型魚です。4~5年が経った80cm以上のもの で、ブリは成長段階で名前を変えることから「出世魚」という縁起魚に選ばれています。
ブリは日本近海の、琉球半島を除いた北海道南部から日本海南部、太平洋付近に生息しています。
ブリの美味しさの魅力はとろっとした脂と、こりっとした食感にあります。冬の寒ブリは特に栄養価も高く、脂がのっており、格別の美味しさです。
「ブリ」名前の由来
ブリと名付けられた由来は諸説あります。
では、ブリという呼び方はどうでしょうか。
また別の説は、江戸時代(1603年~1868年)に活躍した本草学者である貝原益軒(かいばらえきけん)が、元禄12年(1699年)に書いた語源辞典「日本釈名」に記された一文に取り上げられています。
一年で最も美味さが増す寒ブリの時期12月には、ブリに注目を集める「ブリの日」なる記念日まであります。12月20日がブリの日 となったのは、「2(ブ)」「0(輪)」と読む語呂合わせから提唱されたようです。
ブリの養殖業
ブリは需要の大きい魚として養殖が活発に行われています。もじゃこを漁獲し、成魚に育てています。
ブリの養殖は、昭和2年(1927年)に香川県(旧引田町)にて始まりました。「築堤(ちくてい)式養殖施設」 と呼ばれる方法で、海水をそのまま利用した飼育が最初と言われています。
現在、ブリの養殖上位3県は鹿児島県、愛媛県、大分県と、ブリが好む暖かい海流の地域での養殖が盛んです。
天然ブリはアニサキスなどの寄生虫の心配を耳にしますが、養殖ブリは原因となる餌が管理されているため、寄生虫はつきません。
各地で生まれたブリのブランド
ブリの身に最も脂がのって美味しくなるのは冬ですが、それは春の産卵に向けて栄養を蓄え、越冬する時期 だからです。
自信の持てる商品は、他との差別化を図るため、産地を前面に押し出して商品化されます。
寒ブリの到来の地として名高い石川県漁協が立ち上げた「天然能登寒ブリ」 は、冷たい日本海で締まった身と腹身の脂肪含有量が30%以上という脂の旨味を強みにしたブランドです。
富山県氷見漁協が立ち上げた「ひみ寒ブリ」 は上質な脂ののり方が格別と言われ、鮮度の高さを誇る寒ブリの絶対王者として君臨しています。
福井県の美浜町と漁業協同組合は、日向漁港で水揚げされたブリを4~5日水槽で泳がして活け越しし、独自の基準を設けて選別し抜いた1割程度のブリを「ひるが響」 としてブランド化しました。
また、養殖ブリもブランド化が進んでいます。「豊(とよ)の活ブリ」 と呼ばれる養殖ブリを育て、他の産地との違いをPRし、地域の活性化を図っています。「かぼすブリ」 として地域ブランドの付加価値を保っています。
鹿児島県東町漁協では、オリジナル飼料を与えて育てた「鰤王」 という養殖ブランドブリを打ち出しています。
宮崎県串間市の沿岸に広がる日向灘で養殖されている「黒瀬ブリ」 は、出荷三ヶ月前から餌に唐辛子を混ぜて、唐辛子の成分カプサイシンの力でほどよく脂ののった身質に育て、歯ごたえと色合いを追求したブリをブランド化しています。
ブランドブリを名乗れるのは、定められた基準をクリアしたものだけなので、その品質には保証があります。
ブリにまつわる小話
ブリは日本特有の魚であり、また「年取り魚」としても正月には欠かせず、古くから馴染み深い魚のため全国各地で根付いた呼び名に違いが見られるなど、話題に事欠かない魚です。
「年取り魚」に選ばれたブリ
「年取り魚」という言葉を耳にしたことはありますか?
大晦日のご馳走は、1年を無事に過ごせたことを感謝し、新しい年を迎えられることの喜びと願いを込めて年神様へ奉納 したものです。人々は、それを下げた物をいただくのです。
日本列島の東と西は、大断層の糸魚川静岡構造線が大まかな境界線となり分かれています。
ブリは稚魚から成魚への段階で名前を変えていくことから、出世魚と呼ばれます。門出を祝う気持ちを馳せた のでしょう。
美味しいブリの郷土料理
ブリ料理のいろはは、各地で違いが見られバラエティーに富んでいます。
山深い長野県松本市では、塩ブリに加工された富山湾のブリが輸入され、めったに食べられない贅沢なご馳走として重宝されてきた歴史があります。
他にも、富山のブリを漬物にしたブリかぶら漬け、高知のタレぬたを浸けて食べるブリの刺身など、ブリの美味しい食べ方を探すときりがありません。
ブリ好きが起こした騒動
寒ブリの美味しさは、遥か昔より争いの火種となるほどだったとわかる、歴史的な出来事を一つ紹介しましょう。
紀通は5歳の頃、父から受け継いだ伊勢田丸藩の藩主となります。海に近い田丸藩は海産物に恵まれ、紀通は美味しい海の幸を楽しんで暮らしていました。
福知山藩は内陸部(現在の京都府福知山市)にあり、海の幸は容易には手に入らなくなりました。
寒ブリは献上品ともなる藩の貴重な資産でした
「頭を落とした魚を送る」ということは、とても失礼で縁起の悪いことでした。
人々の希望をのせた「ブリ」
日本列島沿岸を泳ぐブリは、昔から日本人の生活と共に長い年月を過ごしてきた、馴染み深い貴重な海の幸です。立身出世を願う縁起のよい魚 で、皆を魅了する美味しさをもっているという事実でしょう。
ブリが幼魚から成魚となるまでに呼び名を変えるのは、その段階で姿や味に違いがあるからです。
ブリは寒くなる師走頃に旬を迎えることから、漢字で魚篇に師を合わせて「鰤」と書き、身の特徴となる脂(アブラ)を略したブラが訛って「ブリ」と呼ばれるようになったとも言われています。
お節料理や郷土料理として、日本の各地にブリの美味しさが伝承されています。
ブリは、全国各地で様々な食べ方をされています。
冬のご馳走であるブリは日本人に愛され、安定した供給を保つために養殖業が盛んになりました。
ブリの基礎知識を頭の片隅に置くと、普段の店頭で見るブリのブランドに目が留まり、美味しい食べ方もひらめきやすくなるでしょう。
[2024-02-16 作成/2024-10-11 更新]
(c)ふるさと産直村