



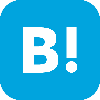

鱈の子であるたらこ
たらことは鱈の子(卵巣)を意味していますが、一般的に塩漬けに加工された食品を指して呼びます。
北海道白老町の虎杖浜で生産されたものはブランド化され「虎杖浜たらこ」として有名です。
海外から冷凍で輸入されるスケトウダラの卵巣と比べ、虎杖浜で漁獲された新鮮な卵巣を使用するので、たらこの持つ旨みが活きた高品質な商品となります。
また東日本大震災で大きな被害にあった宮城県石巻市は、世界三大漁場として有名な「金華山沖」で沢山の良質な魚が漁獲されます。
かつて石巻漁港はたらこ加工生産量日本一を誇っていました。
災害の爪あとはまだ残っていますが、現在多くのたらこ工場が営業を再開し金華ブランド復活に活気づいています。
明太子とたらこの違いは、地域によって少し差があるようです。
明太子とは一般に福岡名物の辛子明太子を指し、たらことは塩漬けにされたものを指しています。
しかし福岡を中心とする西日本地方では辛子明太子は辛子明太子であり、唐辛子を使っていない塩漬けにされたものを明太子と呼ぶ人が多くいます。
おもしろいですね。
たらこの栄養素
たらこの塩漬けに使われるのは、スケトウダラの卵巣です。
たらこは鱈の子ですが、マダイの卵巣は見た目が黒く、卵が筋でつながっているため、たらこの加工には向いてないようです。
塩漬けする前の卵巣を生たらこと言うのですが、焼きたらこと区別するため、塩漬け加工後のたらこを生たらこと称する場合もあります。
食塩水で洗浄した生の卵巣を食塩で漬け、見栄えを良くするため食用色素で赤く染めたものを「紅葉子」と言います。
もともとの色は肌色ですが最近では無添加・無着色の健康志向商品が好まれる傾向にあります。
またたらこには不眠やイライラの症状を改善し、肌の調子を整え、男性性機能維持などに働く栄養素が含まれています。
「子沢山の縁起物」ですので、結婚式の引き出物として人気があります。
たらこの赤はトッピングとしても縁起のよい色として好まれていますので、お正月のお餅に添えると鮮やかになりますし、「先を見通す」と縁起のよい蓮根と和えても美味しくいただけます。
辛子明太子はスケトウダラの卵巣から作られます
博多の名産品として有名
辛子明太子には、スケトウダラの卵巣が利用されています。
スケトウダラの産卵期は11~4月で、山口県北の日本海からオホーツク海が主な産地となっています。
辛子明太子と言えば、福岡県の博多の名産品として知られていますが、その元は太平洋戦争前後の山口県下関市でまぶし製法の辛子明太子が作られたのが発祥と言われています。
韓国からスケトウダラの卵巣を塩辛にしてトウガラシをまぶした保存食が持ち込まれたのです。
もともとタラの卵巣の塩漬けは、何百年も昔から漁師の間で好まれていたようです。
韓国ではキムチのようにトウガラシやニンニク等と漬け込まれ、食されてきました。
戦前、釜山に在住していた博多の老舗「ふくや」の社長である川原俊夫さんが、調味料に漬け込む方法で熟成させる辛子明太子を開発したという説もあります。
昭和24年、博多の辛子明太子の誕生です。
初めて漬け込み製法の辛子明太子を販売された1月10日は、ふくやの販売開始記念日にちなんで「明太子の日」となっています。
博多で愛された辛子明太子が日本中に広まったのは、東京オリンピックの年の、東京大阪間の新幹線開通が大きなきっかけとなったようです。
家庭での温かなごはんに添える一品だった辛子明太子も、今はパスタやサラダにも活用され、世界へとその味が広がっています。
辛子明太子の栄養分
さまざまな調味料が染み込んだ辛子明太子には、多くの栄養分が含まれています。
血管の老化を防ぎ脳の活性化が期待されるDHAや、動脈硬化の改善や中性脂肪を減らす効果のあるEPA、ナイアシン、ビタミンB1、B2、などが摂取できます。
またトウガラシに含まれるカプサイシンは脂肪の燃焼を助ける働きがあります。
ただ、塩分が多めなので適量をいただくようにしましょう。
今、市場には多くの辛子明太子の種類が出ていますが、国内産のスケトウダラで作られている商品は、流通の1割程度といわれています。
贈答品に利用される高級品は、500gで2万円するものもあります。
自宅用には明太子の皮がちぎれた状態の「切れ子」と呼ばれる型崩れしたものや「ばら子」と呼ばれる粒状になったものが購入しやすい値段で販売されています。
辛子明太子は生ものなので保存期間は長くありません。
冷蔵庫で約2週間、冷凍庫で保存しても約2ヶ月ほどです。
ご購入後は、お早めにお召し上がりになった方がよいでしょう。
全国へ向け販売するにあたり、食中毒事故や不正表示を防止するため、全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会では「表示・衛生管理士検定試験」が実施されています。
福岡の特産品をより安心して消費者の方々へお届けするため、数々の取り決めが守られているのです。
スケトウダラは北太平洋に多く生息する海水魚
スケトウダラの生態
北の海の代表とされるスケトウダラは北太平洋に多く生息し、マダラより小ぶりで体長は約60センチほどの大きさをしているタラ科に属する海水魚です。
生息する海流や環境により魚体が大きく異なるようで、日本海では少し小ぶり、オホーツク海や太平洋では大きく成熟します。
主に甲殻類や貝類や小魚などを食べて成長し、肉食で成魚が稚魚を食べる「共食い」も見られます。
タラ科に属しますが、下顎が上顎より少し前に出ていてヒゲがないというマダラとの違いがあります。
1年を通して水揚げされ、鮮魚は比較的安価で販売されています。
12月~4月に産卵期を迎えますが、メスは水深400mほどの海底において数日間隔で複数回に分け20万~100万粒の小さな卵をばら撒くように産みます。
スケトウダラが子孫の残す知恵として、天敵に食べられても追いつけないほどの量を産み命を繋いでいるのです。
スケトウダラは雄雌一対で1ヶ月かけて産卵、放精を繰り返します。
たらこや明太子に利用されるスケトウダラの卵巣
スケトウダラの卵巣は、たらこや明太子に利用されています。
特に鮮度の良いスケトウダラの身はマダラより美味しく、高級魚として扱われますが、スケトウダラの身はマダラ等に比べ鮮度の低下が早く、しかも冷凍にするとスポンジ状に変質するるため向かず、練り製品としても使用できませんでした。
しかし、北海道立水産試験場が1960年に開発した冷凍すり身化の技術によって、肉質の変化の問題が改善され、加工原魚としてすり身にされるようになりました。
スケトウダラの多くは、ちくわや蒲鉾などの練り物などに加工され、私たち日本人に大量に食べられています。
冷凍すり身の技術は、インスタントラーメンや電気炊飯器と並び、戦後の日本の食における三大発明のひとつと言われています。
スケトウダラはクセのない柔らかな白身で、味付けの薄い煮物や焼き物として食べられています。
寒い時期には雑煮や鍋の具として人気があるタラですが、スケトウダラは見崩れをおこしやすいようです。
脂質のないさっぱりとした身なので、ムニエルや天ぷらなどで食べるのが美味しいでしょう。
スケトウダラの名前の由来ですが、佐渡で多く漁獲されていたことから、「佐渡」を「すけと」と読み「佐渡鱈」と書いて「スケトウダラ」と呼ばれるようになったと言われています。
味が良く好まれていたのでこのような愛称がついたのでしょうね。
スケトウダラは韓国で「明太(ミヨンテ)」と呼ばれています。
「明太子」とは、その卵を示し日本人が作った言葉だそうです。
辛子明太子で有名な福岡
福岡という都市
福岡県は日本海側に位置する九州北部にある県。
全国20市の人口50万以上の政令指令都市のうち2市(北九州市・福岡市)が福岡県にあり、人口約5百万人となる九州最大の県です。
かつて産炭量が日本一だった筑豊炭田や有明海海底の三池炭田で炭鉱の町として栄えていました。
アジアの諸都市を身近に感じながら、豊かな自然と都市機能を兼ね備えた魅力ある都市です。
福岡は古くから中国朝鮮との交流があり、志賀島では後漢の光武帝が倭奴国に与えたとされる金印が発見されています。
学問の神様として知られる菅原道真が祀られている全国約12,000社の総本宮である大宰府天満宮には、受験生や観光客など世界中から年間約700万人の参拝者が訪れています。
近隣の海外の主要都市まで1000km圏内と近く、北九州空港、福岡空港、北九州港、博多港などから海外の主要都市への航路が確立されています。
東京より近くに上海があり、海外から多くの観光客を迎え賑わっています。
また留学生の受入体制も整っており、受入人数は全国第3位となっています。
2011年3月12日には博多駅から新幹線が開通し、鹿児島まで1時間19分で行けるようになりました。
ラーメンや明太子、ソフトバンクホークスが有名
福岡といえば、博多ラーメン・もつ鍋・めんたいこ・あまおう・と美味しい食材が思い浮かびます。
食べ物だけでなく、王貞治監督が率いるプロ野球チーム福岡ソフトバンクホークスの本拠地であることでも有名です。
スポーツでは、日本プロサッカーリーグのアビスパ福岡も福岡に拠点をおき活躍しています。
交通アクセスが充実している福岡ですが、都心部にある福岡空港は、博多駅から地下鉄でなんと5分。
日本一便利な空港と言われています。
アジアの空の玄関口である福岡空港は東京、成田に続き日本で3番目に利用者数が多い空港です。
しかし滑走路は1本しかなく、都市部である騒音の問題を考慮し、午前7時から午後10時までの制限がある中、なんと滑走路1本あたりの離着陸数が日本一なのだそうです。
また、海の玄関口である博多港からの外国人旅客数は日本一となっています。
近年は国際海上コンテナターミナルの整備に力を入れ、北米・欧州航路のコンテナ船が寄与し、取扱量の3分の1が輸出で、中国向けにトヨタ自動車の輸出車量が増加しています。
博多どんたくは全国最大規模の動員数を誇ります
福岡市は東区、博多区、中央区、南区、城南区、早良区、西区の7つの区で構成されています。
博多区には福岡の中心核となる「博多駅」「博多港」「福岡空港」があり、陸海空の玄関口となっており、多くの人が行き交います。
毎年ゴールデンウィークには全国でも最大規模の動員数を誇る福岡人の祭り、博多どんたく港まつりが開催されます。
約830年前から続くこの祭りは、1179年に病気で亡くなった平重盛への恩を謝すため始まり、博多の年賀を祝う櫛田神社のお祭りとして行われた博多松囃子が起源とされています。
「どんたく」とはオランダ語「ゾンターク」が語源で、「日曜日」を意味しています。
明治時代に休日に行われたことから「博多どんたく」と呼ぶようになりました。
どんたくといえば、シャモジを叩きながらのパレードが印象的です。
祭り好きな商人の妻が賑やかな囃子の音色に誘われ、シャモジで拍子をとり踊りだしたのが始まりと言われています。
5月3日、4日は、福岡市民と観光客とで220万人もの人が集まったと発表されました。
最終日の夜は、圧巻の総踊りで、博多の街はエネルギーにあふれ返ります。
博多と言えばラーメンだけではなくうどんも
博多と言えば、とんこつラーメンを思い出す人が多いかもしれません。
博多は、博多祇園山笠の生みの親とされる円爾が、うどんとなる麺を宋から持ち込んだ地としても知られています。
福岡式のうどんはコシがなく柔らかい麺が特徴で、麺を茹でたあとに水で締めたりしません。
いりこベースの甘めの出汁で、たっぷりの葱を入れて食べます。
丸天やごぼ天入りが博多の名物うどんです。
魚のすり身を揚げた鹿児島のさつま揚げのような練り物を、博多では「天ぷら」と呼んでいます。
丸天とは、かき揚げのような天ぷらではなく、おでん種のような丸い練り物を言います。
ごぼ天うどんは博多発祥として知られています。
このごぼ天はごぼうの入った練り製品ではなく、衣で揚げたごぼうのかき揚げだったりします。
おもしろいですね。
また、博多のうどん定食には定番で「かしわ飯」が付いています。
博多で「かしわ」とは鶏肉を指します。
人参、椎茸、ごぼうを入れた炊き込みご飯で、九州北部の郷土料理となっています。
贈答とは手紙や詩歌、品物を贈ったりすること
古くからある習慣
「贈答」とは手紙や詩歌を贈ったり、品物を贈ったりすることです。
相手を思い、喜ばせるために贈る物で、季節の挨拶や祝い事などは「進物」といい、使い分けられています。
どちらも、古くから人と人とのより和やかなお付き合いのために生まれた習慣だと言えます。
贈答品や進物には「熨斗」という飾りが添えられます。
熨斗はアワビを薄く削った物を干して引き伸ばしたものを不老長寿の縁起物として添えたことが始まりです。
長期保存がきき栄養価の高い干し鮑は、その匂いで邪気を払うとされ、贈り主の心情と贈答品の穢れのなさを象徴するものとして用いられました。
現在では鮑に見立てた黄色い紙を六角形に和紙で包んだ折り熨斗が主流になっています。
のし紙にあるリボンのような飾り紐を「水引」といいます。
使用する色で意味が大きく異なり、祝いの時は赤白や金銀の色が使われ,弔事には黒白・黄白・青白・銀が使われます。
白は左側になるように結ばれます。
結ぶ本数は奇数で、5本に束ねたものが基本となっています。
諸説ありますが、5本は贈る側と贈られる側の指の本数で、お互いの手が握り合う形を想像させます。
結び方は大きく2種類あり、それぞれ意味が込められています。
「花結び」は何度もほどいて結びなおせることから、繰り返しが喜ばれる出産や御祝に用います。
「結び切り」は二度とないことを願い繰り返しを避けたい弔事、病気や災害見舞いに用います。
目的や用途に合わせて、相手に失礼にならないよう基本的な意味を知っておくとよいでしょう。
気持ちも一緒に贈りましょう
贈り物をするという事は、相手にこちらの気持ちを贈ると言う事です。
金額の大小や量の多さで選ぶものではありません。
贈るのは物ではなく、相手を思う気持ちなのです。
私たちは、1年を通して幾度も贈り物をする機会があります。
お中元・お歳暮など、お世話になっている方には直接渡すのがマナーでしょう。
しかし年末の慌しい時期にゆっくりと贈答品を選ぶ時間もなく、まして遠方の相手との都合を合わせる事も難しいのが現実です。
最近ではインターネットや、直接デパートからの配送が主流になってきているようです。
父の日・母の日の贈り物や入学・進学・卒業のお祝い、または特別な記念日なども、前もって予約発送ができるので活用されるとよいでしょう。
贈り物にはぜひ送り状を添えることをお勧めします。
日頃の感謝やお祝いの言葉は、具体例を加えることでより気持ちが伝わりやすくなります。
普段は面と向かって言うのが恥ずかしいような言葉も、贈り物は気持ちを伝えられるよい機会になるでしょう。
もちろん、受け取る側にもマナーがあります。
感動や喜びを素直に表現し、お礼をしっかり伝えることです。
宅配で受け取った時も直接お会いして戴いた時も、3日以内で電話や手紙で改めてお礼を伝えるとよいでしょう。
贈り物は喜ばれるために心を込めてするものですから、手元に届いた事を伝え、喜びの表情を見せることで相手は安心し嬉しくなるのです。
[2016-11-14作成/2024-10-11更新]
(c)ふるさと産直村




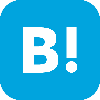
~ 関連リンク<links> ~
