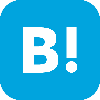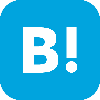うなぎについての雑学・豆知識




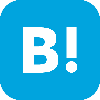

鰻で夏の健康な体を維持
夏場になると鰻を食べる人も多いのではないでしょうか?
鰻のかば焼きやうな丼など、いろいろな料理で親しまれてきています。
鰻をたれにつけて焼いたときのあの香ばしい感じは、なんとも人々を惹きつける香りがしますね?
鰻は、味がおいしいのも確かですが、一方で健康の部分でもメリットが色々と期待できる食材でもあります。
鰻には、ビタミン群が豊富に含まれています。
たとえば、ビタミンAには体の免疫力を高める効果があるといわれています。
夏場になると猛暑のせいで、ばててしまう人も多いのではないでしょうか?
しかし鰻を食べることで、ビタミンAの力によって抵抗力が増します。
その結果、健康的な体を維持しやすくなるわけです。
その他にも、ビタミンB1やビタミンB2、ビタミンE、ビタミンDが含まれています。
また脂質が豊富に含まれています。この資質は先ほど紹介したビタミンAの吸収効率を高めてくれる存在ですので、非常に重要な栄養分でもあります。
だから、夏ばてに良いと人気があるのですね。
その他には、DHAやEPAといった栄養分も鰻には豊富に含まれています。
これらの栄養分には、血中のコレステロール値を低下させる効果があるといわれています。
コレステロールの値が高いと、動脈硬化や高血圧になってしまうリスクが高まってしまいます。
鰻を食べることによって、このような生活習慣病の予防効果も期待することができるわけです。
鰻はただおいしいだけでなく、私たちの健康を維持するためにも欠かせない食材といえます。
鰻の蒲焼きには地域差があります
鰻の食べ方といえば鰻の蒲焼き。
もともと蒲焼きにはさまざまな魚を材料にしたものがあり、サンマなどは今でもよく食されています。
しかし実際「蒲焼き」と言われれば大半の人が鰻のそれを連想することでしょう。
それくらい密接に関わった食べ方といえます。
蒲焼きとは体を開き、頭部と骨を取り払った状態に串を刺して焼いた調理法です。
その特徴はなんと言ってもタレをつけること。
このタレで蒲焼きの出来栄えが左右されるといってもよいほどです。
最近では市販されているタレを使用する家庭が大半ですが、作る人によってさまざまな風味のタレを工夫できるのもこの調理法の楽しみでしょう。
焼いている時のあの食欲をそそる香りも鰻の蒲焼きの大きな魅力です。
江戸時代からとくに盛んに食べられるようになった鰻の蒲焼きですが、現在まで続く地域差も知っておきたいところ。
まず調理法。
関東ではあらかじめ蒸したうえで焼く方法がポピュラーで、ふっくらと柔らかい食感が特徴。
一方関西では蒸さずに直接焼く方法がポピュラーで歯ごたえのよさが特徴となっています。
もうひとつは身を開く位置。
よく知られている話ですが、関東では背開き、関西では腹開きとなっています。
その理由は武士の町である江戸では腹開きは「切腹」に結びつくために縁起が悪い、一方商人の町大阪では腹開きは「腹を割って話す」に結びつくために縁起がよいとされていたからです。
その伝統が現在でも受け継がれているのです。
こうしたローカルな調理方法や価値観の違いなどを知っておくとますます蒲焼きの魅力を味わえるのではないでしょうか。
蒲焼きを美味しく食べる為に
鰻には、いろいろな調理法があります。
その中でも比較的オーソドックスな手法として、鰻の蒲焼きがあるのではないでしょうか?
しかし素人は鰻を購入してさばいて、かば焼きの調理をするのは正直言ってかなり難しい作業です。
そこで通常は、スーパーなどで販売されている、調理された状態の鰻の蒲焼きを購入しているのではないでしょうか?
これでそのまま食べるのもいいでしょうし、ご飯の上に乗せることでうな重にするのもいいでしょう。
調理された鰻の蒲焼きを食べるときに、皆さんはおそらく温めると思われます。
この温め方を少し工夫することで、かなりおいしく料理を変身することができます。
鰻の蒲焼きを見てみると、たれがたっぷりとついているものも多いのではないでしょうか?
しかしこのたれは、見た目を重視するためであることが多いです。
着色料や保存料が多く含まれている可能性もあります。
そこでまず、水道水を使ってきれいにたれを洗い流してしまいましょう。
たれを洗い流した後、グリルを使って、弱火で5分程度鰻を温めます。
この時、水道水で洗い流してしまっていいのかと思う方もいるかもしれません。
しかし、通常市販の鰻の蒲焼きを購入するとたれが付属しているはずです。
このたれを食べる直前に鰻にかければ、十分な味を堪能できるはずです。
食べやすく鰻をカットすれば、鰻の蒲焼きの完成です。
ちょっとした工夫なので、ぜひ、実践してみてください。
濃い口醤油、みりん、砂糖、酒で作る簡単な蒲焼きのタレ
鰻といえば蒲焼き、蒲焼きといえば鰻といってもよいでしょう。
それぐらいポピュラーなイメージが定着しています。
この蒲焼き、鰻の美味しさを引き出すことができる理想的な調理法と言われていますが、その一方でタレに大きく依存している面もあります。
素材のよさとタレの魅力の両方が揃ってはじめて本当の蒲焼きのよさを味わうことができるわけです。
最近ではスーパーなどで鰻を購入した場合、蒲焼き用のタレがついてきます。
それを無意識のうちに使っている人も多いでしょう。
しかし専門店で蒲焼きを食べたことがある人ならわかると思いますが、店で作られたタレと商品についてくるタレでは味わいがまったく異なります。
「こんなタレを使った蒲焼きなど蒲焼きとは認めない」という頑固な食通の人も少なくありません。
そんな蒲焼きのタレですが、自宅で作ることも可能です。
ちょっと手間がかかりますが、自宅で作れるようになれば蒲焼きの魅力が倍増することでしょう。
材料は濃い口の醤油とみりん、砂糖、酒。あとできれば鰻の頭や骨が用意できれば最適です。
まずみりんと酒を合わせた状態で沸騰させ、そこに砂糖を入れます。
その後醤油を混ぜ合わせて再び沸騰、最後に20分程度煮込みます。
煮込む時間が長くなればなるなど濃厚になりますから、好みに合わせて調節するとよいでしょう。
最後にアクを取り除いてろ過すると完成です。
鰻の頭と骨を用意できた場合にはしっかりと焼いた状態で最初の段階で混ぜ合わせておきます。
自分だけの蒲焼きのタレを作れるようにしておけば鰻の調理がますます楽しくなること間違いなし。
鰻の魅力をもっとよく知るためにも、試しに作ってみてはいかがでしょうか。
タレを自作する際の注意点
鰻といえば、かば焼きをイメージする人も多いのではないでしょうか?
ウナギのかば焼きのたれの香ばしさが、なんとも食欲をそそりますね?
ところで、蒲焼きのタレは最近のスーパーで販売されているかば焼きを見てみると、付属品としてついているケースが多いのではないでしょうか?
またスーパーなどの調味料のコーナーに行ってみると、蒲焼きのタレが販売されていることもあります。
こちらを使って、かば焼きを作っても問題はありませんし、おいしいです。しかしできることなら、自分で作ってみたいと思っている人もいるかもしれません。
タレを作るときには、注意しないといけないこともあります。
まずタレを作るときには、砂糖やみりんをベースに醤油で味を調整することが多いです。
このため、ちょっと目を離したすきにタレが焦げてしまうこともあります。
そこで、たれに熱を加えているときには目を離さないようにすることです。
そしてこまめになべやフライパンを回すことで、タレに均一に熱が加わるように心がけましょう。
またタレに熱を加えるときには、弱火でじっくりと煮込むことが重要です。
ここで沸騰させてしまうと、味が悪くなってしまうので注意しましょう。
蒲焼きのタレも焼き鳥のたれも、基本的には一緒のレシピです。
蒲焼きのタレをマスターできれば、焼き鳥にもチャレンジできるようになりますよ。
その他にも厚揚げに作ったたれを絡めると、いい感じの一品に仕上げることができるでしょう。
たれひとつマスターできれば、料理のバリエーションを増やせますよ。
鰻の場合は胃が多く食材として遣われます
鰻の食べ方の中でももっとも高級感溢れる方法となるのが鰻の肝焼きです。
これは鰻の内臓だけを焼いて食べる調理法です。
「肝」という名称が付けられていますが、実際には肝だけではなく広く内臓が対象となります。
さまざまな魚で肝焼きが食べられていますが、鰻の場合は胃が多く食材として使用されています。
鰻の内臓にはビタミンAが非常に豊富に含まれています。
もともと健康によい食材として広く知られている鰻ですが、肝焼きでもその魅力が損なわれることはないわけです。
肝焼きの特徴としては脂肪分が少ないこと。 蒲焼きや白焼きで食べる場合、あの独特の柔らかさをもたらす脂身が大きな魅力なのですが、それが苦手という人もいます。
また、脂身が多い魚は調理のバリエーションが少ないという問題点もあります。
鰻といえば蒲焼きしか思い浮かばない人が多いのもそれが理由のひとつ。
しかし内臓は身に比べて脂肪分が少ないため、より幅広い料理に役立てることができます。
肝焼きはあくまでその一種なのです。
基本的な調理方法は内臓だけを集めたうえで串にさし、タレにつけて焼く方法が採られます。
方法だけ見れば蒲焼きと同じやり方となります。
内臓ですから、わたしたちの多くが思い浮かべている鰻のイメージとはまったく異なる外見をしており、何も言われずに食べたら鰻だと気づかないかもしれません。
冒頭に挙げた高級感溢れるというのは1度に数匹分の内臓が用意されるから。
どうしても量が限られてきますから、一匹分では賄えないのです。
その分高級感というか、贅沢な料理となります。
お酒のおつまみとしても人気
鰻は料理としてはもちろんのこと、お酒のおつまみとしてもマッチする食材です。
お酒を飲まれる方の間で人気のおつまみとして、鰻の肝焼きがあります。
鰻の肝焼きは、自分でも作ろうと思えば作れます。
まずは苦玉と呼ばれるところがあります。
この苦玉の部分を水の中に入れて、つぶしましょう。
包丁の刃先を使ってさすと、苦玉を比較的簡単につぶすことができます。
水の中に入れておかないと、苦玉の中身が飛び出してしまう恐れがあるからです。
衣服に付きますとしみになってしまいますし、目に入ってしまう危険性もあるので、水の中でつぶすのが無難です。
その上で、鰻の胆を串に突き刺します。
続いて、両面を焼いていきましょう。
一方で、鍋を用意します。
そして鍋の中にウナギのかば焼きのたれを入れて、煮絡ませましょう。
鰻のたれは、自分で作ることも可能です。
しかしたれを自分で作るのは面倒というのであれば、市販のたれが販売されているはずです。
こちらを使ってしまっても構いません。その方が時間の短縮化を図ることが可能になります。
焼き網やなべを使うときには、よく事前に洗っておくことが鰻の肝焼きをおいしく調理するためのポイントといわれています。
きちんと洗っていないと、鍋や網焼き器のところに油気が残った状態になっている可能性があります。
そうすると、せっかくの鰻の肝のところにたれなどの味がしみ込んでいかないのです。
甘辛のたれの中に、鰻の肝のちょっとした苦味が絶妙のハーモニーを醸し出してくれます。
身に比べて脂肪分が少なく栄養分に優れた内臓を使用する肝吸い
肝焼きとともに鰻の内臓を使用した調理方法が鰻の肝吸いです。
身に比べて脂肪分が少ないうえに栄養分に優れている内臓を使用する点に最大の特徴があります。
身は脂肪が多いこともあり吸い物には適していないのですが、内臓ならそのような問題もないわけです。
よく鰻の専門店に行くとうな重やうな丼に添えられる形で出されるケースが見られます。
肝吸いだと意識せずに味わったことがある人も多いのではないでしょうか。
逆に言えばメインの食材として味わったことがない人も多いはずです。
どの魚でも肝はお酒とよく合いますが、それは鰻も同様、夕食の友として味わうとよりその魅力を楽しむことができるのではないでしょうか。
自宅で鰻の肝吸いを作る場合、肝をそのまま購入し、スープと混ぜて作るのが一般的な方法となります。
ただ、どうしても流通・保存の観点から殺菌などが行われており、専門店で食べられるような本来の味わいを再現するのは難しいといわれています。
なお、殺菌の際に摂氏100℃以上で熱すると肝本来の味わいが損なわれてしまうといわれています。
ですから購入の際には冷凍されたものを意識して選ぶとよいでしょう。
一方、蒲焼きに比べて簡単に作ることができるため、手軽に鰻を味わえる方法として魅力です。
鰻の内臓はそれほど量が多くないですから、1度に数匹分の内臓を味わう贅沢な食材でもあります。
タレに多くを負う蒲焼きとは異なる、鰻本来の魅力を味わえる調理法ともいえるでしょう。
肝のエキスがたっぷり含まれたお吸い物
ウナギ料理を食べたときに締めとして、鰻の肝吸いを注文する人も多いのではないでしょうか?
鰻の胆のエキスがたっぷりと出ているお吸い物は美味しいですし、冬場に飲むと体の芯から温めることができます。
しかもうなぎの肝には、ビタミンAやEが豊富に含まれているといわれています。
このため鰻の肝吸いは、栄養価が比較的高い料理としても知られているのです。
鰻の肝吸いは、自分でも作ることが可能です。鰻の胆を用意しましょう。
鰻の胆を見てみると、ふちになっている部分があるかと思われます。
このふちになっている部分を包丁でカットしていきましょう。
そうすると中身が出てきますので、すべてきれいに取り除いてください。
その上で、端の部分をカットして、湯引きをさっと行います。
端のところをカットすることで、内臓に入っているいろいろなものを取り除くことができるようになります。
湯引きをしたうなぎの肝は、水を使って流していきましょう。
今度はだしの準備に取り掛かります。
だしは、100㏄用意しましょう。
ここにお酒を100㏄程度加えて、火をつけて沸騰させましょう。
そして最後に少量の塩を加えることで、味を調えます。
だしができたら、先ほど調理をした肝を加えます。
そしてもう一度熱を加えることで出来上がりです。
せっかくですから、鰻の肝吸いを作った時には、鰻のかば焼きと一緒に召し上がってみるのもいいでしょう。
鰻の肝吸いは調理をしてみるとさほど時間はかかりませんので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか?
鰻料理にアレンジを
鰻の料理というと、うな重やウナギのかば焼きなどをイメージする人もいるでしょう。
しかし鰻料理はほかにも、いろいろとアレンジを加えることも可能です。
たとえば、鰻のお茶漬けなどはいかがでしょうか?
さっぱりとした食べ物なので、少し胃もたれをしているときなどでも食べられるはずです。
お酒を飲んだ時の締めの料理として、食べてみるのもいいかもしれませんね?
鰻のお茶漬けの作り方は簡単です。まずねぎを小口切りにして、水けをしっかりときっておきましょう。
そして鰻は市販のもので結構ですので、一口幅にカットしておきます。
ここまでの下ごしらえができれば、器にご飯を盛ります。
そして茶だしをひたひたになる程度まで注いでいきましょう。
好みでしば漬けやワサビを添えてみるのもいいです。
しば漬けを乗せるのであれば、粗めに刻むと食感を堪能することができます。
ところで茶だしはどのようにして作ればいいでしょうか?
だしをアツアツの状態で、カップ3杯分用意します。ほうじ茶葉を大さじ1杯ほど入れた急須に、だしを注ぎましょう。
ここに塩を少し加えます。
目安としては、塩を小さじ1/3程度混ぜるようにするといいでしょう。
このようにして作った茶出しは、さっぱりしている一方でコクを感じさせます。
鰻の茶漬けの他にも、イワシの缶詰や塩じゃけ、塩昆布などとの相性も抜群です。
いろいろなお茶漬けのレパートリーを増やすことによって、毎日でも飽きずにお茶漬けを食べることができるはずですよ。
鰻そのものの旨味を堪能
夏場になると鰻を食べる人も多いのではないでしょうか?
鰻を蒲焼にして、たれの風味と一緒に堪能するのも醍醐味といえます。
しかし一方で、鰻の持っているうまみを堪能したいという人もいるでしょう。
その場合には、鰻の白焼きを食べることをお勧めします。
鰻の白焼きは、ご飯と一緒に食べるのももちろんいいでしょう。
しかしお酒を飲まれる方にとっては、お酒のおつまみとして欠かせない料理といえます。
特に鰻の白焼きは、ビールや冷酒などのおつまみとしてマッチするといわれています。
夏場の熱帯夜の時に冷たいお酒やビールで鰻の白焼きを流し込むというのも、なかなか乙ではないでしょうか?
鰻の白焼きの場合、余計な調理をしません。
鰻を焼いて、ワサビ塩などを使って軽く味付けをする料理です。
このため、鰻の良し悪しが料理の味を決めるとも言えます。
そこで鰻の白焼きを購入するときには、鰻にこだわってみるといいでしょう。
最近ではデパ地下の食べ物屋がアツいといわれています。
デパ地下を見てみると、鰻を販売しているお店もあります。
そのような中には、鰻にこだわっているお店も結構あります。
鰻というと、浜名湖が有名かと思われます。その中でも上質な鰻を厳選して、鰻の白焼きにしているお店もあります。
地下水を使って調理をしているので、身が引き締まって、うまみを凝縮しているような鰻の白焼きもあります。
鰻というと、少し臭みがあって苦手という人もいるでしょう。
しかししっかりと身を引き締めることで、臭みを解消していて、だれでもすんなりと食べられるような鰻の白焼きも出てきています。
浜名湖周辺ではポピュラーな食べ方
鰻の調理法といえばなんといっても蒲焼き。
それしか思いつかない人も多いのではないでしょうか。
しかし、鰻の食べ方はそれだけではありません。
ほかにもさまざまな調理法がありますが、その中でもとくに鰻本来の風味を味わうことができる食べ方が白焼きです。
鰻の名産地として名高い浜名湖の周辺ではこの食べ方の方がポピュラーだといわれています。
白焼きとは蒲焼きと違い鰻を炭火でそのまま焼いて食べる調理方法です。
蒲焼きとの最大の違いはタレを使用しないこと。
蒲焼きは良くも悪くもタレの出来栄えが味を大きく左右することになりますが、白焼きの場合はうなぎ本来のうまみを味わうことになるのです。
ただ、その分焼き具合が重要になってきます。
焼いた後そのまま何もつけずに食べてもおいしいのですが、わさびやショウガ、大根おろしなどをつけて食べるのが一般的です。
何をつけるにしろ、鰻本来の味を引き出す食べ方が求められます。
白焼きという名称は見た目のまま、素焼きにすると白い身の状態で仕上がるからです。
これまで蒲焼きしか食べたことがない人にとっては「うなぎってこんな色をしてたんだ」と驚くはずです。
鰻の白焼きは焼き具合もさることながら素材のよしあしも出来栄えに大きく左右されます。
それだけに名産地など鰻が身近にあるところでしか普及していない面があるのかもしれません。
ただ、蒲焼きだけで鰻を味わいつくした気分になるのはちょっともったいないのではないでしょうか。
一度ご家庭でうなぎの白焼きを試してみてはいかがでしょうか。
うな丼やうな重、ちらし寿司などはいかがでしょうか?
鰻の食べ方といえばどのようなものを連想するでしょうか。
誰もが思い浮かぶのが蒲焼き。
しかしそれ以外何も思い浮かばない、という人も多いと思います。
ポピュラーな食材のわりには意外とバリエーションに乏しい面もあるのです。
しかし、工夫ひとつでさまざまな料理に活用し、美味しく食べることができます。
まず丼。うな丼をメニューに加える鰻専門店も出てきました。
うな重に比べて高度な技術もそれほど必要なく、スーパーで購入した鰻でも美味しく作れて食べられる点が魅力です。
親子丼のような感覚で卵・野菜と混ぜて作ると家庭的な味わいを楽しむことができるでしょう。
作り方は基本的に親子丼と同じ。
鶏肉の代わりに鰻を用意し、野菜はタマネギ、グリーンピースなど。
煮汁の作り方も同じです。
ポイントとしては野菜を先に入れ、柔らかくなったのを見計らって鰻を入れるようにすること。
鰻のちらし寿司などもいかがでしょうか。
こちらも通常のちらし寿司に鰻を混ぜるだけで簡単に作ることができます。
鰻の持つ独特の食感を味わいながら食べられる魅力的な食べ方です。
鰻の蒲焼きが一尾あれば4人分程度作れるので経済的でもあります。
他に使用する食材は好みに合わせて選びましょう。
ポイントとしては鰻は最後の最後に盛ること。
鰻を使うからといってとくに特別な調理の工夫などが必要ないのも魅力です。
このように、日ごろよく作っている料理にうまく組み入れることでさまざまなバリエーションで鰻を食べることができます。
何より楽しみながら工夫できる点が魅力。試しに何か作ってみてはいかがでしょうか。
鰻の最大の秘密はその生態
わたしたちにとって身近な食材である鰻。しかし魚にしてはずいぶんとユニークな存在でもあります。
あの細長い形、ぬるぬるした掴みにくさ。食べるだけではもったいない魅力があります。
この鰻はウナギ目ウナギ科に属している魚類の一種です。
この分類からもわかるようにウナギで独自の目が作られており、やはり他の魚類と比べてもかなり個性が豊かな名存在であることが窺えます。
なお、中世のヨーロッパで広く食されていたヤツメウナギは厳密には鰻の仲間ではありません。
鰻の最大の秘密はその生態でしょう。
じつはその生態、繁殖方法などはまだ詳しくわかっておらず、調査が続いている状況です。
そのため養殖も非常に難しく、まだまだ量産化が進んでいないのです。
この点も鰻が特別な食材として持てはやされている理由のひとつです。
また、えら呼吸の他にも皮膚でも呼吸が可能なため、ある程度の時間なら陸上でも生活できる点も特徴です。
実際、鰻が生息している地域では道路の上を移動している姿を見ることができるといいます。
また、魚には淡水魚と海水魚の2種類がありますが、鰻はどちらの環境でも生活できる特徴も備えています。
一般的には産卵は海で行い、その後淡水に戻ってくるという降河回遊という習性を持っています。
このように、非常にユニークで謎に満ちた鰻。
そんな魚をわたしたちは古くから食材として愛し、さまざまな食べ方を開発してきました。
研究がまだまだ続いているなか、これらかも身近な食材として愛されていくことでしょう。
鰻の名産地として知られる静岡県にある浜名湖
鰻といえば静岡県の浜名湖を名産地として連想する人も多いでしょう。
浜名湖産の鰻がブランドイメージを形作っている面もあり、ギフトの際などもわざわざ浜名湖産のものを選ぶ人が多いようです。
ただ、実際には生産量そのものは減少傾向が見られ、浜名湖を擁する静岡県も全国トップではなくなっています。
近年では鹿児島県がもっとも多く、続いて愛知県、宮崎県、そして静岡県となります。
ランクだけでなく、生産量に関しても静岡県はトップの鹿児島県の4分の1程度の水準になっています。
また、海外産の鰻の輸入量が増加しているのも浜名湖の鰻の生産量の低下の原因とされています。
ただ、生産量こそ減っているものの、ブランドイメージに関してはまだまだ健在といってよいでしょう。
なぜ浜名湖のうなぎは評価が高いのでしょうか。
それは生産量だけでなく、質や歴史とも関わってきます。
まず日本ではじめて鰻の養殖が試みられた場所であること。
現在でも養殖の試みが行われ続けています。
それから質の高さ。
浜名湖は温暖な気候に恵まれており、鰻が育つのに最適な環境といわれています。
さらに養殖の際には地下400mからくみ上げた天然水を使用しており、その質の高さもポイントです。
また、もともと浜名湖にはシラスうなぎが多く生息しており、もともと鰻の養殖・生産に適した場所であることも忘れてはならないでしょう。
このように、日本における鰻の歴史そのものを担ってきたといっても過言ではない浜名湖。
改めて浜名湖産のうなぎを食べながらそのことに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
温暖な気候の浜名湖
鰻といえば、日本人にとっては浜名湖をイメージする人も多いのではないでしょうか?
なぜ鰻といえば浜名湖というイメージができたかというと、浜名湖がウナギの養殖のルーツであることと関係しています。
湖畔のところに明治24年7ヘクタールの池を作って、そこでウナギの養殖をしたのが最初といわれています。
現在でもウナギの養殖は実施されているので、実に100年以上のノウハウが凝縮されているわけです。
しかも浜名湖はもともと、温暖な気候として知られています。天然水も取れ、ミネラルが豊富ということもあって鰻を飼育するには理想的な環境といわれています。
このため、浜名湖の周辺には、老舗の鰻屋もたくさんあります。
中には創業100年を超えるようなところもあります。
また鰻は東西で、少し味に違いがあるといわれています。
関東は比較的あっさりとしたたれを使うことが多い一方で、関西方面では甘い焼きダレを使用することが多いです。
この両者のちょうど中間に位置することもあって、関東でも関西でもどちらの風味の鰻が食べられるところも魅力です。
また浜名湖の周辺では、鰻に関するお土産物も充実しています。
うなぎパイなどはお土産として聞いたことがあるという人も多いのではありませんか?
またウナギボーンと呼ばれる鰻の骨を使った食べ物も、浜名湖周辺の名物といわれています。
このようにいろいろな鰻の味を堪能することができます。
脂の乗りもちょうどよく、品質にあまりばらつきがないのでいつでもおいしい鰻が食べられます。
日本における鰻の歴史は養殖へのチャレンジの歴史
非常にポピュラーな食材としておなじみな鰻。
かつては高級食材のイメージもありますが、最近ではスーパーで手軽に購入することが出来るようになり身近な存在となりつつあります。
しかし、その一方でまだまだ謎に包まれた部分が多い魚でもあります。
そもそも生態や繁殖方法などが明らかになっておらず、養殖に関してもまだまだ発展途上の状況なのです。
魚の場合、安定供給のためには養殖が不可欠となります。
しかし鰻はある程度の実用化には成功しているものの、莫大な供給に耐えうるような量産化には成功していないのです。
日本における鰻の歴史は養殖へのチャレンジの歴史と言い換えてもよいでしょう。
日本で最初に養殖の試みが行われたのは明治24年。
つまりすでに100年以上の歴史を持っているのです。
場所は浜名湖。
現在でも国内随一の鰻の名産地として知られる場所です。
太平洋戦争中に一時期廃れましたが戦後に復活、現在でも養殖の中心地でありつづけています。
ただ、浜名湖の養殖でも完全な人工養殖とはいかず、黒潮に乗ってやってくるシラスうなぎの稚魚を捕獲する形で行われます。
最近になって人工孵化に成功したものの、生まれたばかりの鰻が何を食べているのかわからない状況なのです。
21世紀に入ってから鰻の生態の研究が目覚しく進み、その実態が少しずつ明らかになりつつあります。
鰻の養殖に関してもこれから進歩していくところなのでしょう。
これからどう進展していくのか、量産化が可能になるのかどうか、期待して見守りたいところです。
天然物と養殖物の違い
現在提供されている鰻を見てみると、天然物と養殖物とがあります。
両者の間には、何か違いのようなものがあるのでしょうか?
実は最近の鰻の養殖を見てみると、かなり技術が向上しているようです。
このため、天然か養殖かを見比べることはかなり難しいといわれています。
少なくても、調理をした後の鰻を見て、両者を区別するのはプロでも至難の業といわれています。
ただし、下り鰻に関しては、養殖と見分けがつくといわれています。
産卵時期を迎えたウナギのことを下り鰻といいます。
下り鰻の特徴として、腹部と側面のところが黄金色を帯びていることが挙げられます。
また皮のところは、普通よりも厚みを増していることも特徴として、指摘されます。養殖の鰻は産卵をすることがないので、このような特徴を持つことはありません。
味に関しては、確実性を求めるのであれば、養殖物の方がいいといわれています。
養殖されたウナギの場合、きちんと環境が管理されている状況の中で飼育されています。
このため、どのウナギも一定の水準の中で育てられていて、食べるものも一緒です。
しかも出荷する前には、きちんと検査を実施しています。
そして基準をクリアしたものを出しているので、外れはほとんどないといっていいです。
天然物の鰻の場合、当たり外れが激しいです。
環境が全く違ったところで生育するので、差が顕著になります。
しかし逆に言えば、最高のおいしい鰻は養殖の中というよりも、天然物の中の一部に出てくる可能性があるとも言えます。
大ヒットを狙うのであれば、天然物となるわけです。
鰻と言えば土用の丑の日
現在、鰻の価格が高騰しているといわれています。
なぜかというと、とくにニホンウナギの生息数が激減していることが背景になります。
生息数の少なさはかなり深刻で、2013年2月には環境省が絶滅危惧種の中に、ニホンウナギを入れているほどなのです。
経済の鉄則として、供給量が少なくなれば、価格は高騰します。
このため、鰻は一般庶民にしてみるとそう気軽に食べられない料理になりつつあるといわれています。
実際仕入れ値が急騰していることもあって、鰻の価格は上がっています。
鰻屋の中には、経費削減などのやりくりをして何とか価格の維持に努めているようです。
しかしそれでも1割程度、料理の価格を値上げしているところもあるようです。
このような状況にありながら、鰻というと土用の丑の日が有名です。
2015年の土用の丑の日は、7月24日と8月5日です。
この時に、鰻屋には多数のお客さんが訪れたといいます。
中には、昼の食事時になると店の前には行列ができるようなお店もあったといいます。
夏のスタミナ食といえば、日本人にとっては鰻です。
そこで土用の丑の日に鰻で舌鼓を打とうと思った人も多いようです。
土用の丑の日はそもそも、江戸時代に鰻屋で商売がなかなか思うようにいかずに宣伝戦略の一環として行ったものが由来しているといいます。
しかし現在では、すっかり日本人の間で土用の丑の日は定着しているようです。
鰻が高騰して、そう気軽に食べられないような時期でも土用の丑の日になれば、鰻屋に足が向いてしまうようです。
土用と土曜は違います
鰻といえば土用の丑の日を連想する人も多いでしょう。
夏の丑の日になるとスーパーや鰻専門店などで盛んに宣伝が行われるようになりますし、実際鰻を食べる人も多くなります。
その一方、そもそも土用の丑の日とはどんなものなのか、よく知られていない面もあります。
「土用」を「土曜」と混同している人も少なくないのではないでしょうか。
土用とは暦の一種で、季節の分かれ目に訪れる周期のことです。
ですから鰻で話題になる夏だけでなく、春夏秋冬、年4回訪れます。
固定化された周期ではなく、毎年時期と期間が変化するのが特徴となります。
なお、「丑の日」とは十二支のひとつ。
土用の期間のうちの丑の日を「土用の丑の日」と呼んでいるわけです。
なお、1年に1日ある場合と2日ある場合とがあります。
この日に関してよく知られているのがその期限。
とくに江戸時代に活躍した平賀源内が考え出したという説です。
知り合いの鰻屋が夏場に鰻が売れない悩みを相談したところ、源内が「土用の丑の日」を宣伝して売ればいいとアドバイス。
その結果大繁盛としたというものです。
ただ、この説は本当なのかどうか曖昧な面もあります。
なお、同じように「丑の日に「う」のつく食べ物を食べると夏ばてしない」という風習が当時あり、それをうまく利用したという説もあります。
他には同じく江戸時代後期の春木屋善兵衛という鰻屋が丑の日と子の日、寅の日にそれぞれ鰻を作って保存したところ、丑の日がもっとも持ちがよかったから、という説などもあります。
このように、由来・根拠こそ曖昧ですが、栄養価に優れた鰻は夏場に食べると夏負けを防ぐことができる食材であることは確か。
これからも土用の丑の日に鰻が食べられる習慣は続くことでしょう。
お歳暮とともに根強く残り、知り合い同士が送り続ける風習
現在でも残る日常の風習のひとつがお中元。
お歳暮とともに根強く残り、知り合い同士が送り続ける風習として続いています。
時期は地域によっても若干の違いが見られますが、通常は7月上旬。
この時期はちょうど土用の丑の日が近づくシーズンでもあります。
そのため鰻がお中元のギフトとして選ばれるケースも多く見られます。
現代のわたしたちにはポピュラーな食材となっている鰻ですが、それでも高級感を感じさせてくれるイメージが残っています。
また、好き嫌いが少なく、誰でも美味しく食べることができる食材でもあります。
そのためお中元の選択肢として適している面もあるのです。
ハムでは工夫がない、カニでは好き嫌いが分かれてしまう可能性がある。
そんなギフト選択の悩みを解消してくれる選択肢でもあるわけです。
それだけに、お中元として送る際にはこだわりを見せたいもの。
せっかくならスーパーの鰻では決して味わえないような本物をプレゼントしたいところです。
選択のポイントとしてはまず産地とブランド。
鰻といえば浜名湖が有名ですが、名高い産地の鰻を選べばそれだけでも相手への感謝の気持ちを伝えることが出来るでしょう。
また、有名店の鰻を選ぶ方法もあります。
それから種類。鰻といえば蒲焼きですが、他にも選択肢があります。
たとえば白焼きは素材そのもののよさを味わえる調理法として人気。
日ごろ蒲焼きしか食べたことがない人に送れば必ず喜ばれることでしょう。
また、蒲焼きにもカットされたもの、長蒲焼き、特大の蒲焼きなどさまざまな種類があるので相手方の家族の人数なども踏まえたうえで選んでみましょう。
価格的にもお中元に適した5000円前後のものが多く、楽しみながら選ぶことができるはずです。
お中元にもよく遣われる鰻
夏場になると、日ごろお世話になっている人たちにお中元が欠かせないという人もいるでしょう。
実は昔ながらの鰻屋の中には、お中元として鰻を贈るサービスを提供しているところも多いです。
鰻をお中元として贈ってみるのはいかがでしょうか?
特に静岡県は鰻が名物として知られていることもあって、鰻屋が多く出店しています。
新鮮な鰻を全国に届けるサービスを実施しているところもありますので、活用してみましょう。
最近では、鰻の配送技術もかなり進化しています。
発送する日の朝に鰻をさばき、調理するのが一般的です。
このため、最高の鮮度の鰻を発送してくれるところが魅力といえます。
しかも最近では、真空パックの技術もかなり進化しています。
調理をしてすぐに真空パックすることで、うまみを逃さないようにしてくれます。
このため、届けられたお宅では、出来立ての味とほとんどそん色ない鰻を堪能できるわけです。
鰻のかば焼きを全国にお中元として送り届けることも可能です。
鰻のかば焼きの場合、たれの味が大きき仕上がりを左右します。
このたれは、それぞれの鰻屋で特別に調味料を調合して作っていることが多いです。
このため、鰻屋によって微妙にたれの感じも変わってきます。
そこでお中元として贈る鰻をどれにするか、味比べをしてみるのもいいかもしれません。
鰻は美味しいだけでなく、ビタミンやミネラルも豊富に含み栄養の部分でもおすすめです。
今回のお中元で贈る候補に鰻を入れてみるのはいかがでしょうか?
[2023-12-10作成/2024-10-11更新]
(c)ふるさと産直村